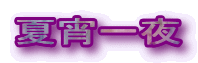
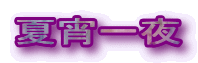
| 43210番ゲット・綾乃さんリクエスト:「ユーリさんのお話の中では、真澄さまはシオリーと結婚して、 シオリーの死後、マヤとくっつく設定ですよね。 そのマヤとくっつく過程をユーリさんなら、いかに料理するのか読んでみたいなぁ〜。 私、恋愛が成就するにしてもしないにしても、その過程が大好きです。」 ――ということで、これは、「聖夜」に続いていくお話です。 |
大都劇場、『紅天女』。本公演。
この演劇界幻の名作は、北島マヤによって月影千草の遺志を継承し、遂に舞台にその全貌を明らかにした。
マヤは、真澄への苦しい恋慕を阿古夜に託し、「世界」そのものの中核存在である「紅天女」役を全うすることで、
マヤ個人の片恋を普遍の「世界」に演繹し、
演劇空間に、片恋をさらに高い次元の事象として、敢然と昇華せしめた。
演技人北島マヤの、完全勝利だった。
いや、人の存在を遥かに越える「紅天女」という「存在」が、舞台空間でマヤに実際に降臨し、
マヤの恋に止揚と昇華とを導いた、そうとも言える。
マヤは、忘れてはいない。
初日に受けた、あの天啓。
マヤと真澄とふたり、全身全霊で融合し、「世界」の中空高く、二人で一つのものとなった、
唯一無二の霊的瞬間を。
以来、どこにどう離れ、人の世の別離を余儀なくされても、マヤには真澄の魂が、心身が、
自分の傍らに側近く、ぴたりと寄り添って片時も離れない実感に、
しっかりと捕らわれてそれは止むことはなかった。
自分を真心から思ってくれる真澄の愛を、マヤは何の疑いもなく信じることが出来た。
マヤには、それで十分だった。
この世に生命ある人間として、また役者として、それ以上の何を望もうか。
演劇界の至宝・『紅天女』千秋楽を終えた3日後、
大都芸能社長・速水真澄と、鷹通グループ総裁孫娘・鷹宮紫織の華燭の典が、
これ以上は望めぬ規模で壮大華麗に執り行われた。
マヤも、公演楽日その日から殺到するスケジュールの間を縫って、列席した。
「紅天女」が降臨したまま、マヤはただ、真澄の現世的な幸福を祈った。
真澄と、自分との関わりは、そうした現世の関わり、繋がりとは、全く次元が違うものなのだ。
「魂の片割れ」。
その強烈な実感が確固としてマヤの内にあり、何物によっても、その実感はマヤから損なわれることはなかった。
水城が動けるようになるまで、マヤには大都所属の男性敏腕マネージャーが取り急ぎ手配された。
夜の夜中であろうと「おはようございます」と挨拶する芸能界。
百鬼夜行のその世界の俗とその垢。
マヤの内面で、真澄との崇高かつ無二の繋がりという確信は些かも揺らぐことは無くとも、
余計な口さがない噂は、否が応にもマヤの耳に入ってくる。
まして、真澄は、マヤが所属を決めた大都芸能の社長である。
『紅天女』の上演権はマヤにあるが、その管理は真澄個人に一任している。
それだけでも、真澄とは、マヤは並みの繋がりではない。
だからこそ、真澄周辺の話題は、所属女優であるマヤの周囲にも、社内外で常に尽きることなく話題にされる。
こと、真澄の事業展開、その忙殺の模様、また、鷹通との提携による各方面への参入などなど。
誰それが口さがなく、新規事業について、マヤの周囲で口にした。
真澄の結婚による鷹通との提携事業の展開、その中核である、中央テレビ傘下への参入。
そのプロジェクト主役として、マヤは抜擢される成り行きとなった。
『紅天女』成功のネームバリューが新鮮なうちに、とは、尤もな企業判断ではある。
だが、マヤにしてみれば、紫織との関係に、厭でもそれは気を回さざるを得ない抜擢でもあった。
中央テレビ系全国ネット、「月9」帯ドラマ、1クール主演。
マヤに割り当てられた、大都芸能の新規プロジェクトである。
日本人ならおよそ老若男女、知らぬ者の居ない超アイドルグループ、そのリーダーを相手にしての、純愛ラブストーリー。
提供、鷹通グループの主立った系列会社。
大都芸能としては『紅天女』以後初の、新規展開である。時の人、マヤの重責も大きい。
が、『紅天女』は、マヤを、演技人として、のみならず、人間として、大きく成長させていた。
そもそもは亡母から植え付けられた、何かにつけてのそれまでの劣等感は、人間としての謙虚な謙遜にマヤの内部で質を変え、
真澄への恋慕は、大人の女性としての豊かな感受性を、マヤの内部に美しい蕾として実らせた。
とにもかくにも、『紅天女』である。『紅天女』がマヤに与えた影響は、そのように大きかった。
華々しいドラマ記者発表の席でも、マヤは羞恥を内に押し隠し、控えめながら、真摯に抱負を語った。
そして、芝居への意欲をキラリと閃かせる瞬間、「平凡」と言われるマヤの顔は、
誰が見ても思わず魅入られるほど、一瞬、はんなりと美しく光り輝いた。
これならば、いける。プロジェクトに関わる誰もが、この記者発表のマヤに、相応の手応えを得ていた。
マヤの演じる役は、共に孤児施設を出て同居する難病の義理の弟を抱えた、貧しく「不幸な」うら若いフリーター。
その弟の入院先で、弟の担当となったインターンが、相手役のアイドルスター。
相手役の役どころも、木訥で純粋な医大生、という設定だった。ラブストーリーは彼にとっても初の挑戦である。
心臓疾患の義弟には、多大な治療費が必要だった。
苦悩の末思い余って、マヤ役は、売春組織に身を売る。
些か時代がかった設定だが、マヤと相手役の清新な若さが、そのドラマ性に現代的な生き生きとした新鮮味を生み出していった。
マヤ役は、事の次第に大きく傷つきながら、それでも健気に明るく弟を見舞い、医大生と知己を得る。
古い安アパートを小ぎれいに整えた自宅でひとり、我が身で稼いだ現金を大きなガラス瓶に詰め込んでゆくマヤ役。
その澄明な悲哀深い葛藤と、孤独ながら健気で清冽な嘆きのマヤの演技が見事で、視聴者はじきこのヒロインに魅了されていった。
ふとしたきっかけから、医大生は、マヤ役が売春に身を落としていることを知る。
爽やかな好青年の医大生役は、なんとかマヤ役に思いとどまらせようとする。そこから、二人のつき合いが始まった。
難病の義弟は、結局、前々から依頼のあった中年夫婦に、義子として引き取られていく。
その別離シーンも、マヤのひたむきな、純な演技が光った。
医大生との恋は、マヤ役の「身分不相応」という引け目から、なかなか進展しない。
が、医大生役の純情で率直な恋心が、かたくなでもの悲しいマヤ役の心を次第に溶かし導いてゆく。
浜辺でのデートのロケシーン。
義弟との思いがけぬ今生の別れシーンのあとで、
医大生役は、マヤに跪き、マヤの手をとって、心からの恋の真実を語る。
若い二人の、心に残る、清々しい恋物語だった。
その後、幾つかの障害を経て、ふたりは一度は別れる。
が、やはり、互いに恋し合う若い二人。求め合う想いは互いに変わらなかった。
夜の舗道で、マヤには初めてのキスシーンロケがあった。
相手役も、苦手とするラブシーンである。
が、意外なことにそのアイドルスターは、本人にも思いがけず、純愛を貫く好青年役の、その役にピタリ、はまった。
マヤは、その呼吸を巧みに捉え、難なく、情愛溢れる切ないほど美しいそのキスシーンを、NG無しで一発で決めた。
その、放映の日。
真澄は、書類の山をデスクに放り、社長室のテレビで、ひとりドラマ放映に見入っていた。
劇的な視聴率を稼いでこそいなかったが、視聴率は安定したレベルを保って落ちることはない。
アイドルスター、そして、マヤの好演と、そのいたいけな純愛カップルが、常に高く評価され人気を博している、との報告である。
1時間ドラマの後半、真澄には問題の、マヤのキスシーンが近づいてくる。
ふたりの躊躇いがちな小さな諍い。医大生役は黙ってマヤの腕を取る。そして、両腕に、小柄なマヤの躰をかき抱く。
真澄は固唾を呑んだ。
マヤが目を閉じ、医大生の胸元に顔をうずめる。
真澄の胸がチクチクと痛んだ。
アイドルスターが、マヤの両の頬を包んで持ち上げる。
そして、ゆっくり、静かに、マヤに口づけた。
カメラの、アップ。
真澄は思わず、ふれ合うふたりのくちびるに、喰い入るように見入った。
“このっ…若造……!”
仕事、と、理性では判ってはいながら、瞬間、真澄の腑は煮えくりかえる。
自分でも抑えられない、狂暴な嫉妬が、真澄の胸中に渦巻く。
“マヤ…俺の、…マヤ……”
ひとり、真澄は胸苦しさに意志で耐えていた。
真澄にとってマヤのくちびるは、少なくともこの日までは、真澄だけのものだったのだ…。
今日はキスシーンだから、まだいい。
だが、ドラマではこれから、ふたりが床(とこ)で朝を迎えるシーンも控えている。
全社で取り組む新規事業の一環とはいえ、
その時を思うと、真澄は胸中はますます苦々しく、荒れ狂うのだった。
真澄は結婚式当日、紫織に、この結婚を仕事上の政略結婚、と宣言した。
紫織への真澄の感情は、すでに冷え切っている。
真澄自ら招いた成り行きとはいえ、紫織のマヤへの執心には、真澄はほとほと辟易していた。
「あなたは形式上、きちんと速水の妻をやって下されば僕になんら異存はないですよ。
僕はあなたには一切手を出しません。その点は安心してください。
理由はあなたが一番お判りのはずだ。
それがお嫌なら、いつでも僕を見限ってくれて結構です。
お綺麗なままのその体で、いつでも鷹宮のお家に帰られるといい。」
“妻になれば…”そんな、紫織の一縷の望みも、真澄はあっさりと非情に打ち砕いた。
それでも紫織は、結婚生活の中で真澄の心が自分に向いてくれることに最後の望みをかけた。
だが、速水邸での紫織の生活は、まさしく「形式上の妻」。
寝室を共にすることもなければ、衣食住のおよそは、真澄は独身時代と変わらずに過ごす。
家人が何と言おうと、真澄のその有り体は、頑として変わることはなかった。
英介にしてみれば、その結婚の実態は、鷹宮への立場も何もあったものではない。
だが、真澄は、決して耳を貸すことはしなかった。
むしろ、英介の「命令」を遂行した以上、それ以上の有無も否やも、決して言及させなかった。
紫織は、日の経つごとに、その不遇な厳しい結婚の破綻という現実に向き合わざるを得なかった。
速水邸で籠の鳥のように、紫織にはもはや、真澄の心を取り戻す機会すら無い。
紫織自身もまた、そうした経緯を、自ら真澄との間に招いたのだから。
真澄は夫妻同伴で出席する公の場にこそ、紫織を伴ったが、私邸では、殊更に紫織と接触しなかった。
紫織には、関係修復のために為す術はすでに無かった。
紫織が望みをかけた結婚は、失敗だった。愚かな、選択だった。
孤独と葛藤の末、よるべなき絶望に陥った紫織は、やがて次第に心弱り、心身ともに深く病んでいった。
マヤのドラマ収録は佳境に入り、恋物語はヤマ場を迎えていた。
「おはようございます!」
マヤはスタジオ入りする。中央テレビプロデューサー、以下、中央テレビスタッフ面々。
“紫織さんの会社の人達…”
紫織の端正な立ち姿が、チラリとマヤの脳裏を掠める。
無論、マヤには真澄と紫織との結婚の実態など、知る由もない。
たとえ、この世で妻となることはなくとも。
そんな悟性が、マヤにはある。そして、演じること、手がけている仕事、それがマヤを根本から支えていた。
スタジオにセットされた、ヒロインのアパート。
紆余曲折の末、前夜、バイクで駆けつけた医大生とともに、初めてふたりが結ばれた翌朝の目覚め、というシーンの撮影である。
「マヤちゃん、よろしくな!」
アイドルスターが、自らも羞恥を弾き飛ばすかのように、マヤに元気良く声をかける。
「はい!」
マヤも、声をかけられて、雑念を振り払った。今は、このヒロインに集中すること。ただ、それだけ。
マヤは、上半身裸となったアイドルスターの若々しい胸を、眩しそうに見上げた。
医大生の腕枕で、半裸の肩をベッドのシーツから覗かせ、ヒロインが目を覚ますシーンだ。
マヤが楽屋着を脱ぎ、半裸でベッドに滑り込んで、撮影開始。
およそマヤには、裸の男の腕枕など、人生始まって以来の経験である。
だが、マヤの演技は、常に脚色に忠実だった。そして、シナリオに記述され演出に求められる「以上」を、
マヤは常に演技していた。しかし。
スタンバイからカメラスタートの間、アイドルスターの腕の中で瞼を閉じていたマヤは、一瞬、遥かに真澄を想った。
“これが速水さんの温もりなら……”
「カーーーット!」
マヤにしては、珍しく不覚をとったNGだった。
「済みません!」
咄嗟にマヤが反応する。演出が怒鳴る。
「マヤちゃんっ、表情違うよっ!」
「はいっ!」
「よしっ!じゃあ、テイク2!」
ADがカウントを取り、再びカメラが回る。今度はマヤは間違いなく、役に集中した。
医大生の純愛に応え、初めて一夜を共にしたヒロインの目覚め、である。
そのドラマ放映の日。
昼日中から真澄の眉間には縦皺が刻まれ、社員誰しも真澄の不機嫌具合に、神妙に恐れをなした。
理由を知る水城は、君子危うきに近寄らず、ソツなく真澄の不機嫌に対応した。
そして、定時は過ぎたものの、さっさと真澄を一人にして、秘書室から退社した。
苛々と真澄は放映時刻を待った。奇妙に時間が長く感じられる。
いっそ、放映など見ずに済ますか。そうとも迷った。
だが、他ならぬマヤの演技、である。マヤがほんの少女の頃から、真澄はマヤの演技を見続けてきた。
“俺ともあろうものが…”
真澄は、自らを叱咤する。だが、
『紅天女』でマヤの到達した境地には、真澄は至れず、未だ真澄は、世人の煩悩のさなかにあるのだ。
やがて、ドラマ開始の時間になった。真澄はテレビのスイッチを入れた。
前回のラストシーン、医大生がマヤ役のアパートに駆けつけるシーンの回想から放映は始まった。
別れを覚悟し悲嘆にくれるヒロイン・マヤを掻きいだいて、医大生が切々と愛を訴える。
そして、ふたり、ベッドへ縺れ込み、マヤがそっと瞼を閉じるところで、顔のアップ。そこで、いったんCMが入る。
次が、翌朝のシーンである。朝の照明。アイドルスターの裸の肩に頬寄せて、マヤが眠っている。
かろうじてマヤの胸を隠すベッドのシーツ。マヤの露わな白い細い肩。
真澄は初めて、それを目にする。真澄の眼は画面に釘付けになった。
アイドルスターの男の手が、その肩を抱いている。
仰向けの男の胸に手を置いて、マヤが男の腕枕で眠っている。
真澄の視覚に訴えるその刺激は、真澄にはやはり酷い衝撃だった。
どれほど望んでも、真澄には手の届かぬ、マヤの素肌。
叶わぬ想いの深ければ深いほど、真澄にはその光景が、とても信じがたいもののように思えた。
マヤのその細い肩を抱くのは、何故自分ではないのか。
まだ真澄が触れてもいない、マヤの素肌。
ドラマの演出以上に、マヤのその姿態は、真澄には、ひどく蠱惑的だった。
“マヤ……!”
真澄は苦衷にあえいだ。
心臓を鷲掴みにされるような、胸苦しさである。
相手役はもとより、その収録現場に居合わせた者すべてを、真澄は呪わしく思った。
やがて、マヤの顔アップ。僅かに瞼が動いて、マヤは目を開けた。そして、うっとりと、相手役を見やる。
身じろぎするマヤを、まだ半分眠っている設定の相手役が、片腕でしっかりと抱き直す。マヤ役が、それに微笑む。
その瞬間、真澄の胸に、鋭い痛みが走った。
男としてマヤを愛してやまぬ真澄には、マヤが他の男のものになることは、どうにも我慢ならない。
演技と判っていても、目の当たりにすればこの苦しさだ。
紫のバラの人としてではなく、マヤが自分に真実、愛情を注いでいてくれることは真澄は理性では知っている。
だが、マヤがするように、それを精神の次元のものとして悟り切ることは、真澄には到底出来そうにもなかった。
それを、心の底から思い知らされた、ドラマ放映だった。
「紅天女」を我が身にやつし、「紅天女」たりえるのは、マヤただ一人だったからである。
やがて、中央テレビ系列帯ドラマのスケジュールは無事終了した。
ドラマは純愛のハッピーエンド、それも、すがすがしい、前向きなジ・エンドとして終了した。
視聴率の数字はそこそこの成功に留まったが、視聴者の評判が非常に高かった。
女性誌、テレビ誌などのアンケートでは、視聴率より内容を評価されて、このドラマはトップを独走した。
相手役アイドルスターが、意外に純愛物の役にはまった、という点、そしてマヤの真摯で清新な役作りに徹した芝居が、
視聴者に大きな共感を生んだ結果である。
「旬の北島マヤ」・売り出しにも、大都は成功した。
ただひとり、その頂点に立つ真澄の胸に、重いつかえを残して。
マヤはテレビ出演に、小劇場での芝居に、と、次々多忙なスケジュールをこなしていった。
主立った演技の仕事が無い時間は、日舞、各種舞踊、基礎訓練など『紅天女』本公演のための地道で地味な稽古に当たった。
中央テレビドラマ出演を終えてしばらく経った頃から、マヤの周囲で、真澄と紫織の不仲説が聞こえるともなく聞こえてくるようになった。
一度、夏の軽井沢での例年の大都芸能主催パーティで、真澄と共にいる紫織を、マヤは見かけたことがある。
主催者として、堂々と隙の無い真澄の半歩後ろに下がって、紫織は真澄に付き従っていた。
が、紫織の顔色はどこか冴えないまま、肌艶も悪く、能面のような微笑を、その貌の表面に貼り付けていた。
マヤは若手のタレントたちに囲まれながら、ついつい、その二人に目がいってしまう。
真澄は、そんな病がちな顔色の紫織を席から下がらせようとでも指示したのだろうか、
その瞬間の、真澄の、紫織を見る、まるで氷のような、冷たい視線。
ビジネスライクで冷酷とも見てとれる、その一瞬の真澄の紫織への態度。
“速水さん……やっぱり紫織さんとうまくいってないの?……”
マヤは、何か見てはいけないものを見てしまったような後味の悪さに、
かぶりを振ってその場をひとり、後にした。
マヤにとって、それが紫織を目にした、最後となった。
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
