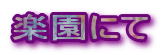
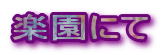
| 80000番ゲットミナ様リクエスト:ふたりの関係はまだ周囲には秘密。業務多忙で長くマヤに会っていない 真澄さんには禁断症状「ボケマス」現象が頻発し、その実害をモロに被る冴子女史が一計を案じる。 それはアマンリゾーツ経営のホテルでの休暇のセッティングである。アマンダリを訪れたふたりは…?? ※ということで、アマンダリの描写は資料不足により過不足があることと思いますが、平にご容赦下さい。 |
会議も半ば過ぎ、水城は、テーブルクロスの下で、横に座る真澄の足を思い切り蹴飛ばした。
真澄は、会議にはまったく上の空。何も耳に入ってはいない様子。一心に何かに思い耽っている。
煙草の灰が長々と燻り、危うくその灰をテーブルに落としそうになるところ、素早く水城が灰皿を差し出した。
真澄が会議の進行とは全く無関係な発言をうかうかと口を滑らしそうになるのを、またも水城は蹴りを入れて、危うく差し止めた。
真澄の失態は、この会議に留まらず、長時間かかってようよう秘書がまとめ上げた書類に、最後の決裁社長印をすべて逆さに押印し、
また新たに決裁印分を作り直さざるを得なかったり。
また、未処理の書類も、時とともに増える一方である。真澄は苛々と社長椅子から立ち上がった勢いで、
そのデスクの書類の山にぶつかり、書類を思い切り床にぶちまけた。
散乱するその書類を順番に並べ直すのも、水城の仕事である。
「真澄さま…」
咎める水城の呆れた口調も、全く真澄の耳には入っていない。茫然として、煙草をくわえて窓辺に佇んでしまう。
「真澄さま!」
真澄はうんざりと、水城の呼びかけに相槌を打つだけだ。
水城は、過去の経験から、真澄がこの状態に陥る時は決まって、マヤのことで頭が一杯になっている時、と弁(わきま)えてはいた。
どのくらいのブランクだったかしら。水城はスケジュールを溯ってみた。丸4カ月、か。それよりも、そろそろプロポーズを考えているようでもあるわね。
もう、そうしてもいい時期であることは確かだわ…。だったら…。
水城はいったん社長室を辞し、旅行代理店の営業マンを秘書室に呼んで、相談をもちかけることにした。
水城が選んだのは、創業以来、世界中のトラベル誌において数々の賞賛を得続けている、アマンリゾーツ経営のホテルチェーンでの休暇だった。
世界のセレブリティー、名のある富豪やハリウッドスターなどもお忍びで利用する、ホテルチェーン。プライバシーを最重要視する要人用リゾートであり、
日本人客も滅多に居ないので、マスコミの目を気にする必要もない。その名も「アマンダリ」。
近年こそ、日本人観光客にも注目されてはいるが、最も高価なクラスであれば、真澄とマヤが訪れても問題ないだろう。
インドネシア、バリ島中央部にある、アマンリゾーツの先駆けとなった由緒あるホテルである。期間は最低限度の、4泊5日。
わずか30そこそこの客室に200名を超えるホテルスタッフと、卓越された質の高いサービスとホスピタリティは群を抜き、
世界中のVIPを魅了し続けている。「アマンダリ」 究極のラグジュアリーホテルと称されるアマンリゾートの原点と言ってもいいかもしれない。
そのような楽園で、限られた時間、という条件付きだが、だからこそ、真澄はマヤに「約束」も取り交わせるのではないか。
果たして、水城の一計や、いかに。
真澄には願ってもない休暇だった。
この時期、インドネシアは乾期にあたる。
東京からは、関空経由で、バリ島デンパサール空港への直行便を利用した方が、到着は速い。
早朝、社用車でマヤを迎え、真澄は羽田に向かった。
羽田を発って、関西空港から日本航空のバリ島行き直行便に乗り換える。空路、7時間。
マヤは、真澄との初めての海外旅行に、天にも昇る心境だった。浮かれて無邪気にはしゃいでは、真澄にまとわりつく。
7時間の飛行も、途中軽くうたた寝している間に、あっという間に到着した気が、マヤにはした。
バリは、夕刻である。
デンパサール空港到着ロビーでは、ホテル専属の現地人送迎員が真澄を見つけ、流暢な英語で、真澄に話しかけた。
「速水真澄さまと北島マヤさまでいらっしゃいますね。ようこそいらっしゃいました。お荷物はこちらで私どもが預かっております。どうぞ、お車へ。」
水城はアマンリゾーツに予約の際、真澄たちに「VIP」の予約を忘れてはいなかった。
ホテルマンが、ゲストの顔と名前を覚えている。これも、アマンならではの、一流サービスの一環である。
「え?え?どうしてあたしたちだ、って判ったの?」
旅の荷物を運ぶ手間もなく、手ぶらでマヤと真澄はロビーを出てすぐの黒塗りの送迎車に案内された。
「さすが水城くんの手配だ。手抜かり無いな。これもホテル側のサービスなんだよ。」
バリの中心街を抜けて、車で約1時間。ゆったりした高級車の車内は居心地よかった。
車外の景観は、やがて森と田園の、バリの風景に転じていく。
バリ島のちょうど中心に位置する村ウブド。
1930年代から欧米のアーティストたちを惹きつけ、現在もバリ芸術の中心となっている。
この村のメインストリートを抜けて、車で約5分。
アマンダリの小さな標識を目印に、車が1台やっと通れるほどの細い道に入る。
鬱蒼と茂る木々の間に小さな集会所や店が現れ、本当にこれがホテルに繋がる道かと危惧する頃、道はぐっとカープした傾斜を下り、
エントランスに滑り込んだ。
エントランスには壁が無く、回廊をつなぎあわせたようなシンプルな造り。そのままアユン川を見おろすカフェにつながっていく。
カフェからは、渓谷に流れ落ちるかのように錯覚させる、有名なプールが見える。背後に茂る木々とは対照的に、渓谷の彼方まで景観は広大に広がる。
ウブドの渓谷に佇むバリの至宝、と賞される所以である。
この近辺では、ヤシの木の高さ以上の建物の建造は許可されていない。夕刻を迎えたバリの、紫色の空。甘く気怠い空気は、アマンダリに満ちている。
現地人のスタッフ男女二人、両手を胸に合わせ、心和む笑顔で、真澄とマヤを出迎えた。
およそホテルのロビー、とは称し難い、落ち着いてシンプルな、決して飾らない穏やかな雰囲気が漂う。
ロビーのテーブルに運ばれたミックスジュースのウェルカムジュースを飲みながら、真澄がチェックインをしてるいと、
GM(ゼネラルマネージャ・支配人)が挨拶に訪れた。
アマンダリでも最近建設された最高額のヴィラ(別荘)、US$2900の滞在客には、当然の仕儀だろう。
こちらも達者な英語で、優雅な挨拶が述べられる。
マヤは、注文もしていないのに運ばれたジュースを不思議に思いながら、真澄がこれまた達者な英語でGMと会話をしているのを、
狐につままれた面もちで眺めていた。ジュースは、日本で口にするものとは全く異なり、天然の果実と幽かな青草の匂いがした。
アマンダリは、「バリニーズ・ヴィレッジ・スタイル」を意識して建造された。
客室は、すべて一棟一棟独立したヴィラ(別荘)形式。
プライベート重視、の設計であり、周囲に点在するウブドの村々と同化するような建築である。
ホテルの敷地と外部との間にはこれといった仕切がなく、ウブドの村の様子を模したスタイルで石畳の通路を挟み、30のスゥィートヴィラが点在している。
アマンダリでは、客室30に対してスタッフ約200名。一室あたり6名のスタッフが、種々のサービスを提供することになる。
現地人スタッフの女性が、真澄たちの滞在するヴィラに向かって、案内してくれることになった。
ヴィラに向かう小道は、高い塀で囲まれてはいるが、実際にバリ島の村を歩いているような感覚を起こさせる。
小道は巨木を避けて曲がり、古い祠には、毎夕、昔から住む村の住人が花を供えにやってくるという。
真澄は、その会話をマヤに通訳してやった。マヤは、日本での生活の現実とはかけ離れた、この空間の醸し出す雰囲気に、すっかり気圧されていた。
バリの家を模したがっしりした木の門を開けると、そこは、プライベート・エステート。
マヤは思わず、わあっと歓声を上げていた。
高い天井、広々とした室内。ガラス戸の中はひんやりと冷房が効き、低く民族音楽が流れている。
今回は3ベッドルームに2段のプライベートプール付きの、最も優雅なヴィラ。
蚊帳に包まれた広いベッド。その後ろ側には広々としたクローク。何ヶ所ものガゼボ(寝椅子)。屋外のバスタブは床のレベルを下げたサンクロンバス。
入浴すると、外の蓮の池と同じ目線になるという。頭上には、室内に活けられた緑が揺れる。
テラスには、バレイと呼ばれる東屋があって、涼しげに風が吹き抜けている。
風に乗って、竹を打つ、緩やかで優しい音色が聞こえてきた。プールサイドで夕暮れに演奏しているガムランだろう。
バリのどこにでもある村の夕暮れ。アマンダリとは、サンスクリット語で「平和の精神」という意味だという。
めまぐるしく厳しく多忙な大都芸能社長の身にあって、真澄には今、何よりも必要なのは、マヤ。そして、「癒し」をもたらしてくれる時間と空間。
こうして、日常の都会を抜け出して、自然と一体となった極上のヒーリング・リゾートにひととき、身を隠すのは、最高の贅沢だった。
これから、4日間、この「世界で最も優雅な隠れ家」で、マヤとふたりきり、たっぷりと楽園の時を過ごすのだ。
メイン・リビングのテーブル脇には、既に真澄たちの荷物は運ばれており、テーブルにはウェルカムシャンペンとウェルカムフルーツがセットされていた。
そして、木彫りのキーホルダーのついたルームキー。バリ美術のセンス溢れる英語でのカードメッセージ。
荷ほどきして、クローゼットに荷物も仕舞い、さて、このシャンペンとウェルカムフルーツをどうしようか、という頃合い、まるで見計らったように、
白い制服の現地人スタッフが3人、ドアノッカーをノックして、やってきた。シャンペングラスにナイフとフォーク、皿を運び、
まずは、派手なシャンペンシャワーで、ウェルカムの団欒を演出する。マヤはきゃあきゃあと、降り注ぐシャンペンに歓声を上げた。
シャンペングラスに注がれたシャンペンを口にしてみる。まろやかで、上等な泡立ちが、のどごしに優しい。
スタッフが手際よくフルーツを切り分け、皿に取り分けていく。一つ食べると、またひとつ、別なフルーツが差し出される。
その間、床に降り注がれたシャンペンはいつのまにか綺麗に拭われていた。
「あの…、自分でできますから…。」
次々差し出される南国の果実に、いささかマヤは面食らって、つい日本語で口にしていた。
スタッフは、和やかな笑顔を絶やさず、
「You are welcome。」
と、作業を止めない。真澄はというと、スタッフのサービスを、当然のことのように、悠然と、もてなしをうけていた。
もう、夕食も間近い。フルーツのおおかたを一口ずつ賞味して、真澄はウェルカムフルーツは終わりにした。
真澄が席を立つと、スタッフが黙々とテーブルを片づける。そして、いつのまにか、彼らは姿を消していた。
「マヤ、来てごらん。」
真澄は遥か窓の遠くを眺望できるガゼボに半身を横たえ、マヤを膝の上に抱いた。
「黄昏が美しいだろう…。」
「ほんと…。ここはいったい何処なのかしら…。」
「俺たちだけの、楽園だ。何をしても、誰からも、いっさいが自由だ。」
真澄の腕の中で、マヤはこの異文化の情緒溢れる非日常の空間に、なんとも圧倒される一方だった。
じきに、ディナーの時間が来た。アマンダリには「一流」のシェフを擁するレストランもあるが、食事はヴィラでもレストラン同様、食べられた。
スタッフが、粛々とディナーを運んでくる。真澄はバレイ(東屋)に食事をセットするよう命じた。
バリの夕風を感じながら、味わう、地元料理。「ナシ・コンプリート」。
カクテルには、真澄はダイキリを、マヤにはチチをオーダーした。
スタッフが、手際よくディナーの給仕をする。人に仕えてもらうことに慣れていないマヤには、どうにも、この微に入り細に渡った給仕には、
恐縮してしまってならない。よほど、人に仕えられることに慣れていないと、このアマンのサービスは使いこなせないのだ。
かたや、真澄はというと、会社でも自宅でも、仕えられることには慣れきっている。悠々と、給仕を受け、ひと皿ごとの間に煙草も燻らしている。
真澄のその、洗練された挙動。テーブルマナー。
マヤには、急に、真澄が遠い人のような気がした。「育ちの違い」を見せつけられたような気が、マヤにはする。チクリと、マヤの何処かが痛んだ。
真澄は実に気分良さそうに、風景を眺め、夕風を受け、食事を進めている。マヤは、なんとか給仕についていこうと、必死である。
マヤはうっかり、並べられたフォークをバラバラと床に落としてしまった。すぐさま、代わりがテーブルに用意される。
「あ、どうも…。」
咄嗟に出るのは、マヤにはやはり日本語だ。マヤはせっかくの料理の味も、気後れと緊張で判らなくなりそうだった。
そうこうするうち、ディナーもあらかた片づき、カクテルのお代わりも済んで、真澄は席を立った。
このアマンのサービスの一環として、部屋で個別にオーダーしたものにも、一切サインは要らない。真の優しさ、というものを、あらためて気づかされる。
「ごちそうさま…。」
マヤはスタッフに日本語で声をかける。真から和やかな笑顔が、返ってきた。マヤは、不思議な気がした。見ず知らずの他人なのに、こんな笑顔…。
それが、アマン一流のサービスなのだ。まるで旧知の間柄のような、優しさと親しさを、スタッフは笑顔で提供するのである。
マヤには、どこか知らない異国に迷い込んだような気もしてきた。そう、間違いなく、ここは異国。インドシナ。日本とはまるで異なる自然と風土。
真澄はリビングに戻ると、最も広いガゼボに長々と横になった。
「速水さん、食べてすぐ寝ると、牛になっちゃうわよ。」
「牛になったら、俺を嫌いになるか?」
「…もうっ!」
「きみの方が牛じゃないか。」
ハハハと声をあげて、真澄は心から愉しげで、くつろいでいた。
「ここにおいで。」
真澄はマヤをガゼボの横に呼んで横たわらせた。
マヤに軽く口づけると、真澄はすうっと、あっという間にうたた寝に落ちていった。
マヤは、そんな真澄を傍らに眺めながら、このベッドルーム3つの広大なヴィラに、いったい幾らの値段がかかっていることかと、溜め息をついた。
マヤにとっては、海外旅行は初めて、それも、こんな贅沢で高級な旅行は、想像外だった。
真澄が一緒だから助かったようなもので、マヤひとりでは、英語はおろか、とても、このホテルのサービスには戸惑って、ついていけそうにもない。
真澄とこれから一緒に過ごしていくうちには、こうしたことは、よくあるのだろうか。
“もし、もし速水さんと結婚なんてしたら…どうなっちゃうんだろう…” “あたしなんて…とうてい、やっていけそうにもないわ…”
マヤが寝返りを打つと、真澄がようよう目を覚ました。三面に開けたリビングの窓の外には、木々の上に満天のアジアの星空。
マヤは自然、窓際に歩み寄っていた。そのマヤを後ろから真澄はかき抱いた。
「一緒に風呂に入ろうか…。」
マヤの耳元で、真澄は甘く囁く。
「え…。」
「恥ずかしがることはない。ここは俺たちしかいないんだ。」
室内にある2つのシャワーブースの外、屋外に、大理石のバスタブがあった。真澄はバスタブに降りて、湯を満たす。
籐の籠にバスタオルとバスオイルがセットされている。旅装の衣服をさっさと脱ぎ捨て、真澄は片側のシャワーブースで身体を洗う。
マヤもタオルで髪をまとめて、シャワーで身体を流した。
「おいで…。」
全裸の真澄が、やはり全裸のマヤの手をとって、大理石の石段を下りる。バスタブにふたり、身を横たえると、なるほど、
外の庭の池に浮かぶ蓮の花と、同じ目線の高さになる。バリの人々が、いかに自国の文化を大切にしてきたか、の証左かもしれない。
「蓮の花、か…。」
「なあに?」
「極楽浄土に咲く、仏さまの花だよ。ここは極楽、というわけだ。」
夜風が、温い湯に浸かる二人の髪をなぶってゆく。
「天女さまも傍にいるし、な。」
真澄は笑って、ゆらゆらと湯を揺らすマヤの乳房に手を伸ばした。
「…あっ…」
真澄は湯の中で、すべらかなマヤの乳房を掌で弄んだ。
じきに、その乳頭が赤みを増してくる。リラックスの入浴半分、戯れ半分の、入浴だった。
「上がろう。ベッドは広いぞ。」
籐の籠からバスタオルを拾うと、真澄は体を拭くのもそこそこに、メインの寝室に向かった。
マヤはバスタオルで身体を覆い、髪を解いてドレッサーで整えた。家具も、バリ文化の香り高いそれらが取り揃えられている。
主寝室の壁には、バリ美術による壁画が描かれていた。
蚊帳を払いのけて、真澄はキングサイズより広いベッドに長々と身を横たえた。
マヤが、そっとベッドに上がってくる。真澄はマヤの腕を思い切り引っぱり、すぐさま身体の下に組み敷いた。5人は寝られる広さだった。
「いったい、どれくらい我慢させられたんだ?」
「俺はこうしたかった。マヤ…。」
マヤは顔を赤らめる。湯上がりで艶めかしい肌が、真澄の言葉で、さらに火照る。
真澄はマヤの身体を覆うバスタオルを剥ぎ取ると、素早くマヤに接吻しながら、数ヶ月の空白を埋める勢いの嵐のような愛撫で、マヤの全身を翻弄した。
幾度となくマヤはベッドに躰を転がされ、全身の隅々まで、真澄の愛撫の嵐に晒された。
久しぶりのマヤの肌を堪能した真澄は、マヤの膝を立たせ、大きく広げた。そして、マヤが抵抗する間もなく、素早くマヤの秘所に口づけた。
マヤが思わず身を捩り、嬌声をあげる。執拗なほど、指先で、くちびるで、舌で、真澄はマヤを誘惑する。
マヤの興奮も、否が応でも高まった頃、真澄は体勢を立て直すと、マヤの膝を抱え込み、欲情のまま思い切り深くマヤを差し貫いた。
あられもない歓喜の声を、マヤがあげる。マヤの内部での、圧倒的な真澄の存在感。マヤにしても久々である。マヤは甘い眩暈を覚えた。
久しぶりに迎えた性愛の交感の時。二度、三度。繰り返し、真澄は、飽くことを知らず、マヤを求め続けた。
たっぷり3時間は、そうして激しく愛し合ったろうか。
マヤが先に降参した。真澄はまだ、飽き足らない思いだが、日にちはゆっくりある。急ぐことはない。
「何か飲むか?」
「…うん…喉がカラカラ…。」
真澄は24時間のルームサービスで、飲み物を注文した。部屋に備え付けのバティック(更紗)の室内着に袖を通すと、真澄はルームサービスを待った。
じきに、ボトルで冷やされたバーボンとオレンジジュース、氷とグラスのセットが届けられる。
真澄はグラスにオレンジジュースを注ぐと、ベッドに朦朧と横たわるマヤに運んでやった。キャスターごと、寝室に運ぶ。
そして、自分は一杯だけスタッフが作った水割りを口にする。煙草に火を点けて、深く燻らすと、煙草が旨かった。
真澄は室内着を脱ぎ捨てると、ベッドのマヤに寄り添った。
そして、めくり上げたシーツを引っ張りあげると、マヤの背を愛撫しながら、広いベッドに身を投げた。
夜も更け、いつしか、ふたりは互いの素肌に寄り添って、深い眠りに落ちていった。
真澄が目覚めると、マヤはまだぐっすりと寝息を立てていた。
起こしてやろう…。真澄はマヤの躰のそこここを丹念に愛撫する。
昨夜の激しい愛の痕跡が点々と残るマヤの白い肌は、実に扇情的だった。真澄はマヤの乳房を口に含む。
舌で、その尖端を転がすと、マヤが幽かに呻いて、ぼんやりと目を空けた。
「あ…速水さん…。」
真澄はくちびるを離し、マヤの顔を覗き込んだ。
「おはよう。お目覚めか?」
「うーん、よく寝た…。おはよう。」
「シャワーを浴びてくるといい。朝食、といっても、もう昼近いな。食べたら、マッサージに行こう。」
“マッサージ?”
またしてもマヤは、真澄のペースにことが進むのに躊躇したが、逆らったところで仕方がない。
シャワーを浴び、洗面を済ませて着替え、ドレッサーで髪を整えると、真澄も着替えを済ませてクローゼットを閉じたところだった。
「食事はテラスにしよう。」
真澄は電話で、軽いブランチを注文した。好きな場所で、好きな時間に食事をとれるのも、アマンダリならでは、である。
じきに、スタッフがやってきて、窓を開け放ち、広いテラスに食卓のテーブルをセッティングする。
バリ料理のブランチは、そよ風も爽やかな光溢れるテラスの風光によくマッチした。食後のミックスジュースが、ことのほか、マヤには気に入った。
ブランチを終えると、食事と同時に予約したマッサージルームの案内が来た。このアマンダリでは、特別にマッサージルームが設営されている。
水城じきじきの推薦だった。アマンダリのマッサージは特に有名とのことである。
蓮池に面したマッサージルームでは、実に多種多様なメニューが用意されていた。ハネムーナーには、このうちの2時間コースが無料、という。
「婚約者じゃあダメなのか?」
真澄は案内のスタッフに冗談を言う。マヤは耳ざとく、エンゲージ、という単語は耳にした。エンゲージ…婚約…婚約!?
「えっ?ここで裸になるの?ふたりとも?」
マヤは酷く戸惑って狼狽した。
「そうだ。欧米人ならカップルで受ける当たり前のサービスだぞ。」
言うと、真澄は脱衣籠に、さっさと衣類を脱ぎ捨ててゆく。
そして、メニューを決めるとオーダーし、マッサージ台に俯せになった。腰にタオルが掛けられる。
「ほら、マヤ。きみも早く。エステティシャンを待たせるんじゃない。」
真澄が選んだメニューは、2時間コースの“マンディ・レンパ”。
緊張感を解き放つ1時間のアロマオイルマッサージの後、伝統的なハーブウオッシュで、ヨーグルトと共に全体を洗い流す。
そして、最後に数々のスパイスと南国の花びらを浮かべたバスタブに身を沈めて、マッサージ終了、というメニューだ。
マヤは、昨夜の愛撫の痕跡がなんとも恥ずかしかったが、真澄もエステティシャンも、全く意に介していない。それが当然、という風情だ。
だが、確かに、極上のリラクゼーションではあった。
アロマオイルの独特な香料の芳香、鳥のさえずりや木々のざわめきの中、施術を受けていると、
まるで幽玄の世界に漂うようなひとときを味わうことができた。
こんな贅沢があったなんて…。
マヤは自分の今までの世界がいかに狭い範囲のものに限られていたのか、ひしひしと痛いほど感じた。
マッサージを終えて、ふたりはヴィラに再び案内された。木々の香りが芳しい。
ヴィラに戻ると、寝室もリビングも、綺麗に元通りに整頓されていた。そして、ベッドのシーツには昨日とは違う英語詩の栞が挟んであった。
マッサージで身体はみごとにほぐれたが、喉が渇いたな、という頃合い、スタッフが、ジュースを運んできた。
これも、ならではのサービスだろう。
「注文もしてないのに、どうして喉が渇いた、って判るのかしら…。」
「ゲストの気分を先回りしてサービスする。それがここの特徴だそうだ。」
マヤはまたしても、身分不相応、という気がしていた。
「プールもあるが、泳ぎは明日でいいだろう?」
三面採光のリビングは明るく、美しく、遠い空の青が眩しかった。
「街に出るのもいいが…俺はここでマヤとふたりきりがいい。いいか?」
「…うん、そうね…、こんな広いお部屋でふたりきり、なんて、すごい贅沢だけど…。」
この旅に出るにあたっては、真澄は密かにそろそろ「プロポーズ」を、と、タイミングを図っていた。
いつ、どのタイミングで切り出そうか。それには真澄の心中も穏やかではなかった。
3つあるベッドルームのうち、採光も明るい寝室に、真澄はマヤを抱き上げて入った。
午後の陽光が、天窓から差し込んでくる。テーブルには大きな南国の花束が活けられていた。花の香りに、むせ返るようだった。
真澄はマヤをベッドに横たえると、静かに口づけしながら、ゆっくりブラウスのボタンに手をかけた。
「速水さん…こんなに明るいのに…。」
「明るいからいいんだ。光の中で、マヤを抱きたい。初めてじゃないか。」
マヤは羞恥に俯いてしまう。手際よく、薄着も下着もすっかり脱がされ、マヤは思わずシーツで全裸を隠した。
真澄はフッと笑いながら、衣服を脱いでいく。マッサージで肌つやを増した、真澄の逞しく均整の取れた躰が、陽光の中、マヤの目の前に現れる。
真澄の肩が、天窓の陽光を反射する。眩しげに、マヤは真澄の裸体を見あげた。
真澄は、マヤがかき抱いていたシーツをサッと剥ぎ取った。咄嗟にマヤは、胸を両腕で覆う。
「恥ずかしいことじゃない。見せてくれ。マヤ…。」
真澄の甘い囁きに、マヤは、躊躇いながらも素直にそっと、両腕を脇に下ろした。
「綺麗だ…。」
アジアの陽差しの中の、マヤの裸体。その姿態を、真澄は心の眼に焼きつけた。これほど美しい、これほど愛おしいものが、他にあろうか。
俺のものだ…俺だけの…。
真澄は逆巻く熱情のまま、明るい午後の寝室で、マヤへの愛に、行為で没頭していった。
いくら抱いても、まだ、足りない。完全に、マヤを、自分だけのものにしたい…。
マヤは従順に真澄の愛に従っているのだが、真澄にはまだ足りない気がしていた。
長い、激しい睦み合いのあと、軽いまどろみにふたりは落ちていった。
うっとりとマヤが目を覚ますと、天窓にはラベンダー色の空が覗き、どこからか、ガムランの音が聞こえていた。
楽園、か…。
マヤはぼんやりと、舞台以外では口にしたこともないその非日常の言葉を、思い浮かべた。
真澄は、呼吸もしていないかのように、ピクリとも動かず静かに眠りに落ちている。長のとしつき、慕い続けた、その横顔。
それが手を伸ばせば届くところにある、その幸福。
でも、婚約?結婚?…あたしなんかには、とてもムリだわ…。こんな世界ばっかり、ついていけそうにない…。
そう考えると、マヤの胸はひどく痛んだ。
マヤが身じろぎすると、真澄がすっと目を覚ました。
「ああ、もう夕方か…。腹は減っていないか?食事にしよう。」
「シャワーを浴びてくるね。」
「ああ。俺もだ。」
シャワーを浴びて着替え、ラタンのドレッサーに腰掛け肌と髪を整えるマヤを、真澄は腰をかがめて後ろから抱きすくめた。
「夕飯はどこで食べようか?」
「…どこでも。速水さんにまかせる…。」
どこか投げやりなそのマヤの言い様に、真澄は多少のひっかかりを覚えたが、特に意に介さなかった。
「今日はフレンチにしよう。それなら、このリビングでいいな。」
真澄の注文からしばらくして、夕食がダイニングテーブルにセットされていく。ふたりは食事を始めた。
欧米人ゲストに人気のフランス料理も、真澄に言わせれば、日本の一流どころにもひけをとらない見事さだという。
マヤはテーブルマナーに気を取られながら、それでも、昨日よりは料理の味に判別はついた。
料理も格別だが、マヤには赤、白ともにワインが特に美味だった。おそらく、非常に高価なものなのだろう。
デザートと珈琲も終えて、スタッフがテーブルを片づけていく。真澄は満足げに煙草を燻らせて、マヤに微笑みかけた。
「旨かったな。」
「…う、うん…。」
マヤが微妙に曖昧な返答をする。が、真澄は深くは捉えてはいない。
「庭に出るか。」
煙草を揉み消すと、真澄はマヤの手をとって、バレイ、東屋に歩み入った。広いガゼボ・寝椅子がある。
木々のざわめきの上には、漆黒の闇。燦々と煌めく星空。遠い、星の瞬き。夜風がそっと、マヤの長い髪をなぶる。
遠くから、ガムランの音色が響いてくる。
真澄はガゼボに腰を下ろし、マヤを横に座らせて肩を抱いた。マヤがそっと身をもたげてくる。
静かな宵、落ち着いた夜の、いいムードだった。
…今なら…口にしてもいいか…?。
真澄は緊張した高校生のような気分になった。
それを、自ら戒める。子供でもあるまいし…。思い切って、言ってしまおう…。今…。真澄は意を決した。
「マヤ…。」
「うん?」
「…結婚してくれないか。」
マヤは絶句した。いざ、ここではっきり、そう言われるとは…。
しばし、沈黙が流れる。
そのマヤの反応の無さに、真澄は怪訝にマヤの顔を覗き込んだ。
「どうした?うん?」
マヤは、まだ口をきかない。
「マヤ…?」
「速水さん…あたし、ダメよ。結婚なんて、できない…。」
「何だって?」
「あたしなんか…速水さんのお嫁さんなんて、とても務まらない…そんな自信なんてない…。」
「どうして!?」
思いもかけないマヤの返答に、真澄は急いて、詰問口調になった。
「あたしなんか、速水さんに相応しくないもの…。」
「君は…俺を愛してくれているんだろう?だったら、それで充分じゃないか。」
「だって…。」
「昔から言うだろう、柳行李ひとつで、いいんだ。」
「…あたしは社交なんて出来ないし、英語も話せないし…だいいち、育ちが違いすぎるわ!こんなホテルだって、贅沢すぎる…。」
「そんなことは君が気にする必要などない。俺はマヤ、きみを永久に俺だけのものにしたいんだ!」
「あたし…あたしは…」
「とにかく、速水さんと結婚なんて、あたしには無理…。」
「マヤ!」
マヤは真澄の腕を逃れて、顔を背けた。
「…じゃあ、いったい、君は俺と、どうするつもりなんだ!?俺が嫁をとって、君は愛人にでもなるっていうのか。」
「そんな!…そんなこと言ってない!速水さんの鈍感!なんでそんな酷いこと言えるの!?」
マヤはいたく、傷ついた。
「だったら、俺と結婚すればいいじゃないか。」
「どうしてそう簡単に言えるのよ!あたしには荷が重いって、言ってるんじゃない!」
「…ということは…君は俺が思うほど、君は俺を愛してくれてはいないのか…。」
「…違うったら…!もうっ!そういうことじゃないわよ!」
「ならば、証拠を見せてもらおう。」
真澄はマヤを強引に抱き上げると、すたすたとヴィラに向かい、まっすぐ主寝室に入っていった。
いささか乱暴にマヤをベッドに横たえ、自分の躰の下に組み敷くと、
「今夜は寝かさない。」
強い口調で、言い放った。
「いや、やめて!」
マヤの抵抗もものともせず、真澄はがっちりとマヤを抱きすくめると、剥ぎ取るようにマヤを全裸にしていった。
そして、マヤが抗う気力も失せるまで、真澄は激しい行為で、夜通し、マヤを翻弄し続けた。
愛している、愛されている、その実感を確かにとり交わすまで、真澄はマヤを決して解放しなかった。
そんなふたりが、疲れ果て、泥のような眠りに落ちたのは、真澄の宣言通り、明け方近かった。
午後も遅くなって、ようよう、ふたりは目を覚ました。部屋にはボトルごとクーラーに冷やされた飲み物と軽食が、ワゴンで届いていた。
真澄はベッドから起き上がると、ワゴンを寝室に運び、グラスにジュースをあけて、マヤに手渡してやる。
「おはよう。疲れたか?」
マヤはシーツを胸まで引き上げると、グラスを受け取った。
「ありがと…身体がどうにかなりそうだわ…。」
マヤは一気にジュースを飲み干した。ワゴンの上部をとりあげると、ベッド用の食卓がセットされていた。
ベッドの上で、ふたりはのろのろと、その軽食をとった。真澄が、子どもに食べさせるように、マヤにサンドイッチを食べさせてやる。
こんなシーン、何かの映画にあったわ…。
マヤは他人事のように、ぼんやりと考えた。昨夜の夜通しの行為から、まだはっきりとは目覚めていない。
食事を終えると、マヤはまたベッドに身体を丸くした。真澄が傍らに座り、その背をゆっくり愛撫する。
さすがに、激しくしすぎたか…。だが、昨夜のマヤの返事を、真澄はなんとしても承諾するわけにはいかないのだ。
「外出用の服は持ってきているか?」
「…うん。…今日は何処かへ行くの?」
だるそうに、マヤが真澄を見あげる。
「夜になったらな。そんなに疲れたなら、またマッサージに行こうか?」
「…ううん、いい。」
「じゃあ、風呂に入ろう。ゆっくりぬるま湯にでもつかるといい。」
真澄は屋外のバスタブに降りていった。
香料のバスオイルも、何種類かふりかけて、湯を満たした。ツンと、甘い香りが湯気に混じる。
マヤを抱き上げると、真澄は大理石のバスタブにマヤを運んだ。
マヤの長い髪が濡れないように、タオルをとって髪を纏めてくるんでやる。
ふたり、バスタブに身を横たえると、午後の翳った陽光が湯面に差し込んでいた。梢を渡ってくる風が木の香りにかぐわしい。鳥のさえずりが聞こえる。
「うーん…。」
マヤは湯の中で思いきり伸びをした。さすがに、こわばった身体もほぐれてくる。
「気持ちがいいだろう?」
「うん、…ほんとね…。」
マヤは、うっとりと眠くなった。確かに、自然という贅を尽くした、至福のひとときなのだ。いつしか、うとうとと、マヤは微睡んでいた。
そんなマヤを、心底愛しい、と真澄は思う。マヤのためになら、自分に持てるものの何物をも惜しくはないというのに…。
真澄はマヤの頬に、そっと口づけた。
ぬるま湯もそろそろ冷めかけてきた。夕空が、燃えるように赤く美しい。真澄はマヤをそっと揺り起こした。
「マヤ、マヤ。」
「あ…あ、寝ちゃった。」
「シャワーを浴びて、支度するんだ。出かけよう。」
マヤが薄化粧を終えると、真澄が何事か電話で注文している。やがて、案内のスタッフがやってきた。
エントランスの前に黒塗りの車が待機しており、促されてマヤは車に乗り込んだ。
「どこへ行くの?」
「ラーマーヤナを観に行こう。」
「なにそれ?」
「舞台だよ。インドの伝説を叙事詩にした舞踏劇だ。言葉はわからなくても、面白いだろうな。」
車はじき、ヒルトン・バリニーズ・シアターの前で停車した。真澄がチケットを買い、小劇場のほぼ中央の席に、ふたりは着席した。
約2万4千の詩節からなるインドの叙事詩「ラーマーヤナ」は、友情や勇気、そして愛を題材にしたラーマ王子の冒険物語である。
実際に演じられる時は、この物語の全てが演じられるのではなく、一部がピックアップされる。
バリ文化の情緒に満ちた衣装、装置、そして高度な技術を要する舞踏、美しい王女の金を織り込んだ豪華な衣装も、見どころだ。
舞台、というだけで、マヤの目つきが変わった。
バリ舞踏は長い歴史を有し、ヒンドゥ教の篤い信仰心に満ちている。
やがて客席が暗くなり、上演となった。
バリ文化独特の凝ったきらびやかな衣装、歌舞伎を思わせるが微妙に異なる化粧、被り物、アクセサリ、小道具、大道具、音楽、照明。
舞台の全てが、マヤにはまったく未知の、異文化のエッセンスに満ちていた。
我を忘れて、舞台の展開に魅入られるマヤを、真澄は満足げにそっと横から覗き見た。
王子、王女や、魔王、魔王の使う魔法、猿の勇者、魔法の弓、戦争とケガ、薬草の効用。そして、一騎打ち。王女の身の潔白を証明するために、
王女は火の中に身を投ずる。結果、王女は火傷ひとつ負うことなく、身の潔白は証明される。
マヤは王女シータ役の、高い舞踏能力に完全に魅了されていた。そして、物語は大団円のうちに終わりを告げる。
マヤは夢中で、楽しい喝采を舞台に贈った。
「凄い…!速水さん!」
マヤは満面の笑みで、真澄を振り返った。真澄も、これ以上はない、という優しい笑顔で、マヤを見つめ返した。
「いい芝居だったな。」
「ほんと!こんな舞台もあるなんて…!」
「あたし、あの王女の踊り、踊りたいわ!」
マヤはすっかり感動と興奮に我を忘れている。迎えの車に乗り込んでも、まだマヤの感激は収まらない。
「ああ、素敵だった…!あたしも、演りたいわ!」
「シータ王女か?」
「そうよ!あんな美しい踊りができるなんて…!」
車はじきアマンダリに戻った。スタッフがヴィラにふたりを案内していく。
道々、マヤは今観劇したばかりのバリ舞踏の振り付けを、ゆっくり真似ている。真澄はそれが面白くてならない。
マヤのことだ。一度観ただけで、シータ王女の見せ場の振りを覚えてしまっていた。そして、知らないインドネシアの言語も、口にしてみる。
マヤにかかれば、すっかり、王女の模倣も板に付いてしまう。マヤの擬態能力の高いことは、真澄もよく知ってはいた。
「せっかくだ、夕食は地元料理にしよう。」
真澄はテラスに食事をセッティングさせた。
ナシ・ゴレン、サテ、チャプ・チャイ、ソト・アヤムなどなど。
唐辛子、大蒜、胡椒、ジンジャー、ターメリック、そこにココナツミルクの甘さ、レモンバジルの酸味など、種々の香辛料の利いたバリ料理を口にしながら、
マヤは舞台のお喋りに夢中になっている。真澄は真から愉しげに、それに相槌を打ってやる。
真澄はアラックという地元の酒も注文していた。椰子の樹液から作る蒸留酒で、アルコール度は35度と、かなり高い。
マヤにはアラックベースのトロピカルカクテルを。香辛料の辛みが、アルコールで飛んでいく。
食事を終え、真澄は昨日同様庭を散策し、バレイ・東屋でマヤと休憩した。夜風が暫しの酔いに心地よい。
「ああ、舞台!あたしには、やっぱりお芝居しかないんだわ!舞台!そこにあたしの全てがある…。」
マヤは酒精も加わって、感慨ひとしおの風情だ。
そうしたマヤに、真澄は言葉を選び、真摯にその真情を口にした。
「マヤ、俺はきみのためになら、世界中のどこのどんな舞台でも、観に連れて行ってやる。必ず。」
「そして、どんな役でも、きみが全力で演じられるよう、必ず、用意させよう。」
「他の何より、俺はきみにそうしてやりたい。そして、演じるきみを、客席からずっと観ていたい…。」
真澄の深い声音。マヤは思わず真澄を振り返った。
「…ほんと?ほんとに?」
「ああ。もちろんだとも。」
真澄がマヤに微笑みを返す。
「嬉しい…。」
マヤはそっと真澄の肩に頬を寄せた。
真澄は腕を伸ばしてマヤのその華奢な肩を抱き寄せてやる。
今、確かに通い合う、ふたりの熱い想い。
亜熱帯の楽園の星降る夜。
俺は…姿やさしいこの花にこそ、やはり心惹かれる。
それを愛してはいかんということでは、俺の生きている意味は何処にある?
おれはこの花をいだいて、ときめく心臓へ押しつけたい。
この一瞬、くちびると頬とにくちづけして、この幸福な苦しい心を注ぎかけたい。
この刹那、マヤ、そのくちびるから、おまえの愛の言葉が聞きたい…。
…そうだ、今こそ、もう一度、マヤにはっきりと告げるのだ。サンタマリア!
祈る思いで、だが確固として、真澄はマヤに告げた。
「そうだ。だから、マヤ…俺と結婚してくれ。そして、舞台の世界で、ふたりで生きていこう、一生…。」
「…速水さん…!」
マヤが顔を上げる。
「…結婚してくれ、マヤ…。」
真澄は両手でマヤの頬を包み込んだ。真澄の瞳の強い光がマヤの眸を射る。
そう…、あたしが愛した人はあなただけ。ずっとあたしを支えてきてくれた紫のバラ。
あたしが舞台に立つ限り、速水さんはあたしを守ってくれる。支えてくれる。今までどおり。これからも、ずっと。
それなら、いい。それだけで、いい。それだけが、すべて。何を躊躇うことがあるの?
一瞬、マヤの脳裏を、これまでの全ての紫のバラの思い出が走馬燈のごとく巡った。
速水さん。あたしの、ただひとりの、あたしだけの、紫のバラのひと…。決して、かけがえのない…。
そしてマヤは、真澄にとり縋った。
「ええ、…ええ!速水さん…あたし…一生、速水さんの観てくれる舞台で、生きていたい…!」
遂に真澄はその念願のマヤの言葉を耳にした。
「マヤ…本当だな?」
「ええ…本当よ…。」
真澄は、マヤをかき抱いた。真澄の胸で、マヤは震えた。
「ありがとう…約束だ…必ず、マヤ、きみを幸せにする…!」
言って、真澄は深々とマヤに口づけた。
涙が一筋、マヤの頬を伝った。
真澄にしっかりと抱き締められ、真澄の腕のなかでマヤはひととき、幸福の夢に酔いしれた。
そして、その夜は、ふたりにとって、忘れがたい生涯の約束の、このうえない甘い夜となった。
翌日、より確かな絆で結ばれたふたりは、ヴィラ付きの2段式のプールで半日、無邪気に戯れた。
そして、帰国前夜、記念の夜を、思いの丈込めて、ふたりは心で、躰で、互いに愛を刻み込んだ。
帰国すれば、ふたりの前途に、素晴らしい未来が開けて待ち受けているような気が、ふたりにはした。
楽園にて。異国の風土が約束した幸福が、ふたりを、いつまでも祝福していた。
後日談。水城は、帰国して出社した真澄をひと目見て、満面の笑みでにっこりと微笑んだ。
「よろしゅうこざいましたわね。真澄さま。」
「マヤちゃんの花嫁姿、楽しみにしていましてよ。」
真澄は、水城のその言葉にふと笑って、遠く、窓の外を眺めやった。
2001/9/18
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
