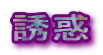
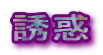
| 295295番ゲット・soleil様リクエスト:いつも多くの男性を魅了するマヤ。しかし、本人にその自覚がないため、 不用心に接してしまう。その結果、襲われそうになってしまうところを速水さんが救ってあげてください。 ※というリクエスト端的なリクエストを頂きました(^^;) さて、どうしましょう? |
北島マヤ主演『紅天女』の成功から1年。
マヤは勇躍、一流女優の名を恣にした。
長年想い続けた真澄とも晴れて想いが通じ、秘密裡に二人の交際が続いていた。
マヤは大都芸能に所属し、時の人となって多忙な芸能生活を送っていた。
大都芸能が毎年夏、軽井沢のホテルで開くパーティ。
大都所属のタレント、歌手、俳優が勢揃いし、各界著名人を迎えて、華やかに交流の饗宴が催される。
看板女優マヤの周囲にも人垣ができ、マヤは精一杯の笑顔で接客に当たっていた。
薔薇色のイブニングドレスを身に纏い、髪をアップにして、マヤは正装していた。
「あなたが北島マヤさんですか。『紅天女』拝見しましましたよ。素晴らしい舞台だった。」
「ありがとうございます。」
「再演の際には、またぜひ観劇したいものだ。」
「また、どうぞよろしくお願い致します。」
「北島さん、サインを頼みます。」
「はい。」
次から次へと、客たちがマヤに群がる。
真澄は遠目に、忙しく立ち働くマヤを窺っていた。
パーティ開始から1時間半、マヤを取り巻く客も一段落した。
「マヤちゃん、お疲れ。喉乾いたろ?」
「あ、黒沢さん。」
黒沢聡。大都所属の売れっ子俳優で、現在収録中のテレビドラマで、マヤと共演している男だ。
「はい、オレンジジュース。」
黒沢はグラスをマヤに手渡した。
「ありがと。はぁぁ、忙しかった。」
「ちょっとベランダに出ないか?」
「うん。ひと休みしたいわ。」
マヤは黒沢とともに、いったん席を外し、会場から続くテラスに出た。
ベンチに腰掛けると、黒沢もマヤに並んで腰を下ろした。
「あぁ、足が棒みたい…」
「マヤちゃん、きみは芝居をしていない時は、まるで普通の女の子だね。」
「芝居に入ると、まるで別人だ。」
「ほんとに驚かされるよ。」
「そう?そうねぇ。お芝居している時は、いつも別人になっちゃうの。昔から。」
「俺も役者として、マヤちゃんには勉強させられるよ。」
「そんな…」
マヤは含羞んで俯いた。
黒沢は、ふっと笑って、鋭くマヤを見つめた。
「可愛いね、マヤちゃん…」
「風がいい気持ち!」
マヤは黒沢の視線からついと逃れて、立ち上がった。
そうした挙動のひとつひとつが、男心をそそるものだとは、マヤはゆめ、知らない。
黒沢は、マヤのイブニングドレスの背中を見つめて言った。
「さて、戻ろうか。」
「はい。」
ふたりはパーティ会場に戻った。
じきにまた、ふたりそれぞれに、人垣が出来る。
マヤはまた、目の回るような接客に、懸命に応対した。
やがてパーティは盛会のうちに終了した。
その夜は、ホテルのスゥィートに連泊している真澄のもとへ、マヤは忍んで行った。
久々の逢瀬である。
マヤが真澄の部屋を訪ねると、真澄は既に着替え、ブランデーを傾けながら、煙草を吸っていた。
「やあ、久しぶりだったな。」
「うん、速水さん。」
真澄はマヤを抱き寄せた。ひととき、しっかりと、真澄はマヤを抱擁する。
「今日は良くやってくれた。俺は鼻が高かったぞ。」
「あーあ、もう疲れちゃった。立ちっぱなしで喋りっぱなしなんだもの。作り笑いでほっぺたが痛いわ。」
「ゆっくり風呂に入ってくるといい。」
「うん。そうさせてもらう。」
真澄が抱擁を解くと、マヤはバスルームに消えた。
しばらくして、マヤが浴室から出てきた。
「ああ、いいお湯だった。」
アップにしていた髪をおろし、上気した頬が艶めかしい。
マヤは着替えをクロゼットに仕舞うと、ソファに腰を下ろし、真澄の飲んでいたブランデーに手を伸ばして、クイクイと飲み干した。
「おいおい、酔っぱらうぞ。」
「いいじゃない。もう、くたびれちゃって…」
言って、マヤは真澄に身をもたせかけた。
「しょうのない天女さまだな。」
真澄は苦笑して、プランデーを注ぎ足してやる。
マヤはグラスを傾け、今度はゆっくりと酒を口にした。
「ああ、美味しい…」
「もう、そのくらいにしておけ。寝るぞ。」
真澄は言ってマヤの手からグラスを取り去り、マヤを抱き上げて、寝室に入り、灯りを消した。
解放感とアルコールの勢いも手伝って、その夜、マヤは真澄の腕の中で放埒に乱れ、深い交わりに我を忘れた。
翌朝早朝、まだ仄暗いうちにマヤは真澄の部屋を出て自室に戻り、東京へ戻る支度を済ませた。
愛されたあとの気怠い身体は、むしろマヤには心弾むものだった。
午前7時。マネージャーの柾木が、部屋にマヤを迎えに来た。
「おはよう、マヤちゃん。今日はドラマ撮りがあるからな。」
「はい、マネージャー。車で一眠りするわ。」
「よし。じゃあ東京へ帰るぞ。」
ホテルで柾木とモーニングを済ませ、マヤは車中の人となった。
「おはようございます。」
マヤは軽井沢から直行でテレビ局入りした。
「おはよう、マヤちゃん。」
昨日のうちに帰京していた黒沢がマヤに声をかける。
「昨日はお疲れ!今日もよろしくな。」
「はい、黒沢さん。」
黒沢は、まじまじとマヤを見つめ、囁いた。
「どうしたの?何かいいことでもあった?」
役者の鋭い観察眼は、さすがに誤魔化せない。
「いえ、別に。私の顔、なにかついてます?」
咄嗟にマヤはうそぶいた。
「今日は何だか、いつになく綺麗だよ。」
「そんなこと…」
マヤは言葉を失って、目を伏せた。
「ふふ、まあいいさ。今日も頑張っていこう。」
「はい。」
楽屋でヘアメイクと着替えを済ませ、マヤはスタジオのセットに入る。
「よーし、シーンナンバー132から行くぞ。マヤちゃん、スタンバイ!」
「オーケーです!」
「はい!視線、5カメ!行きまーす!」
ADがカウントを取り、撮影がスタートした。
その日のマヤは、絶好調だった。
演技は冴え渡り、NGのひとつも無く、周囲の演技陣を圧倒した。
台詞の微妙な抑揚、ほんの僅かの間合い、共演者との演技の呼吸、表情、しぐさ、どれをとっても、マヤは格別光っていた。
順調この上なく撮影は次々進み、すべてのスケジュールをマヤは終了した。
「よーし!終了!マヤちゃん、お疲れさん!」
ディレクターが声をかける。
黒沢が急ぎ足でマヤに歩み寄ってきた。
「マヤちゃん、凄いよ!調子いいなぁ。あと5カットで俺もあがるから、待ってて。一緒に食事に行こう。」
「あ、はい…。」
いつものように、役に入り込んだまま、マヤは頷いてしまっていた。
楽屋で着替え、メイクを落としても、マヤはまだ演技の熱から冷めないでいた。
「マネージャー、今日は黒沢さんと食事に行くから、帰りの送りはいいわ。」
「そうか?あまり遅くなるんじゃないぞ。」
「はい。判ってます。」
黒沢が仕事を終えて、マヤを楽屋に迎えに来た。
「マヤちゃん、お待たせ。行こうか。何が食べたい?」
「あ、何でもいいですよ。」
「じゃあ、六本木にフランス料理を食いに行こう。」
黒沢の運転で、ふたりは深夜に華やぐ六本木の繁華街に出かけた。
六本木でも知る人ぞ知るレストランで食事を進めながら、黒沢は上機嫌だった。
「マヤちゃん、今日は絶好調だったね。」
「きみが本気を出すと、凄いよ。周囲も巻き込まれて、いい演技になる。」
「俺も刺激になった。」
「きみのような役者、ほんとに天才だと思うよ。」
「いいえ、そんな。あたしは…」
「ただお芝居が好きなんです。それだけのことですよ。」
「好きなだけじゃあ、あれほどの芝居は誰にも出来ないよ。」
「俺はマヤちゃんに逢えてほんとに良かったと思っている。」
「他のどんな女優にもない魅力が、きみの演技にはある。」
「これからも、ずっと一緒にやって行きたいな。」
その黒沢の甘言に、マヤは酷く戸惑ったが、
「…黒沢さんのような先輩に、そう言って頂けると、心強いです。」
言葉を選んでマヤは答えた。
「先輩、ねぇ。芝居に関しては、きみの方がキャリアは長いだろう?」
「キャリア…子どもの頃、月影先生に出逢って、お芝居を教えられて、今日まで来たんです。」
「月影千草、きみの恩師だね。」
「ええ。今でも、天国から私の演技を見守っていて下さいます。」
「月影先生の名に恥じないお芝居をしたい、いつもそれだけは心がけているんです。」
「きみは素敵だよ。演技者としても、女性としても。」
食事をあらかた終えて、デザートと珈琲が運ばれてくる。
「マヤちゃん、きみ、好きな人はいるの?」
「えっ!?」
「恋人はいるかって、訊いているんだよ。」
「それは…あの…」
マヤに返す言葉は無かった。
「いないなら、俺とつき合ってくれないか?」
その黒沢の物言いにマヤは混乱したが、律儀にもこう答えた。
「それは…、お仕事としてなら、いくらでもお付き合いします…」
黒沢は一笑に付した。
「ハハハ…俺は焦らないから。少しでもいいから、俺のことも考えて欲しいんだ。」
「とにかく、これからもよろしくな。」
「あ、はい…」
食事を終え、ふたりはレストランを後にした。
「そろそろ帰らないと。」
マヤがそぞろに口にする。
「ああ。送っていくよ。乗って、マヤちゃん。」
黒沢の運転で、マヤはマンションまで送られた。
「じゃあね。今日はありがとう。またな!」
「はい。ご馳走様でした。」
マヤは黒沢の車の発進を見届けると、部屋に帰った。
つき合っている人、か…。速水さんとのことは絶対秘密だし。
つき合っている人がいる、って言えたら、ラクなんだけどな…。
マヤは、内心深く溜め息をついた。
真澄はいつものごとく、大都芸能の地下駐車場で、聖から報告を受けていた。
一通り指示した調査報告が済むと、聖が言いにくそうに口に出した。
「真澄さま、マヤ様ですが…」
「なんだ。また贔屓筋か?」
「いえ、今度は大都の俳優です。黒沢聡。26歳。今撮影中のドラマで共演しています。」
「撮影の日は必ず一緒に食事に出かけているようで。写真週刊誌も、そろそろ気づいております。」
「まったく…またか。判った。ありがとう。よく気をつけていてくれ。」
眉間にくっきりと縦皺を寄せて、真澄は苦々しく、吐き捨てるように言った。
「かしこまりました。何かありましたら、緊急の番号にご連絡します。」
「ああ。よろしく頼む。スキャンダルは厳禁だ。」
「承知しました。では私はこれで。」
「ああ。ご苦労。」
――まったく、マヤときたら。不用心にもほどがある…
真澄は夜の社長室に戻り、黒沢聡のデータを探した。
秋の好日。マヤと黒沢、共演のドラマ撮影は無事クランクアップし、その日はスタッフ、出演者一同で打ち上げが行われた。
一同、テレビ局から赤坂の街に繰り出し、ディスコのワンフロアを借り切って賑々しく華やかな宴席が設けられた。
一同が踊りに興じるなか、マヤは隅の席でぼんやりとフロアを眺めていた。
黒沢がマヤの席にやってきた。
「どうしたの?踊らないの?マヤちゃん?」
「あたし踊りは苦手なんです。」
「飲み物は?空じゃない。注文したらいいよ。」
黒沢はウェイターを手招きすると、スクリュードライバーを注文した。
やがて飲み物が運ばれてくる。
「これなら飲みやすいから、飲んでごらん。」
「ありがとう。」
マヤは乾いた喉にジュースを流し込んだ。
スクリュードライバーとは、ウォッカをベースにオレンジジュースをアレンジした飲み物で、甘口で飲みやすいことは飲みやすい。
ただし、ベースがウォッカなので、飲み過ぎると急に足にくる。足が立たなくなる。
男が女を口説く時、飲ませる飲み物である。
「ああ、美味しい。」
「だろう?」
「もう一杯どう?」
「うん、いただくわ。」
マヤは2杯目も一気に空にした。
ディスコでの一次会もはねて、二次会に移ろうという時、席を立ったマヤは急に眩暈を覚えて、倒れかかった。
「おっと。」
黒沢がマヤを抱きとめる。
「あたし…酔っちゃったみたい…帰ります…」
「俺が送ろう。」
「大丈夫…ひとりで帰れます…」
「夜の街は女の子ひとりじゃ危ないよ。いいから、俺が送るよ。」
マヤのマネージャーの柾木は宴席には同道していなかった。
「なんだ、黒沢、ぬけがけか?」
「送り狼になるなよ。」
周囲から冷やかされて、マヤはますます居たたまれなくなった。
おぼつかない足元でふらつきながら、マヤは歩き出したが、ガクリと膝を折って蹲った。
「そら、マヤちゃん、立って。」
黒沢がマヤを抱き起こす。
黒沢に支えられて、マヤはなんとか歩き出した。
ディスコを出て、一ツ木通りから、黒沢はタクシーを拾った。
写真週刊誌の記者と聖が、その後を追う。
「代々木上原1丁目まで。」
あやしい呂律で、マヤが行き先を告げる。
黒沢は黙って、マヤを抱き寄せていた。マヤは頭がグラグラとして、抵抗のしようが無い。
「運転手さん、行き先変更。246を走って渋谷の先まで行って下さい。」
「えっ…」
咄嗟にマヤには何のことなのかは判らなかった。
「いいから。俺についておいで。」
246号線沿いに、プライバシーを重視したブティックホテルがある。車からチェックインできるため、芸能人などがよく利用するホテルである。
渋谷を通りすぎればすぐそのホテルだ。
「運転手さん、その角のホテルへ行って。」
「くろ…さわ、さん…」
「恐くないから…」
黒沢は甘く囁いた。
タクシーは地下駐車場へ入る。黒沢はチェックインし、無抵抗なマヤを抱きかかえてタクシーを降りた。
ふたりがエレペーターを上がるのを確かめて、聖はフロントに怒鳴り込んだ。
「今チェックインした組のスペアキーを出してくれ!女性の方の連れだ!」
そして聖は自分の車の電話で、真澄の緊急ホットラインを呼び出す。
そのブティックホテルは大都芸能本社からは目と鼻の先だ。車で5分もあれば着く。黒沢の不敵な思いが、聖には手に取るように判った。
「真澄さま、黒沢がマヤ様をホテルに連れ込みました!246沿いのスターラインです!鍵は手に入れましたのでお急ぎ下さい!」
“なんだと!すぐ行く!”
真澄は取る物もとりあえず、社長室を飛び出した。
(間に合ってくれ…!)
エレベーターが降りる時間ももどかしく、真澄は駐車場の車に飛び込み、自分のBMWを急発進させた。
裏道を走って、真澄はくだんのブティックホテル駐車場に車を突っ込んだ。
フロント前で聖が待機していた。
「さ、真澄さま、お早く!」
聖からスペアキーを受け取ると、真澄は蒼白な顔でエレベーターに乗り込んだ。
5階まで上がるエレベーターの速度が、ひどく遅く感じられる。
502と印された部屋を探し当て、真澄は鍵を開けて、部屋に飛び込んだ。
黒沢はちょうど、シャワーを浴びてホテルのガウンに着替え、ベッドに寝かせたマヤにのしかかろうとしているところだった。
「そこまでだ!黒沢!」
「は、速水社長…!」
「大事な商品に手を出すとは何事だ!」
「社長、俺は…」
「問答無用!この子は俺が連れて帰る。きみはしばらく謹慎したまえ!」
真澄は厳然と言い捨てると、あっという間にマヤをベッドから抱き上げ、さっと部屋を後にした。
黒沢は呆然として、部屋に取り残された。
駐車場へ降りると、聖が待っていた。
「真澄さま、マヤ様は…」
「ああ、間に合った。無事だ。」
「写真週刊誌は追い払いましたので。」
「ありがとう。助かった。」
「よろしゅうございました。ではお気をつけて。」
「ああ、ご苦労だった。ありがとう。」
酔いで朦朧とするマヤを助手席に押し込み、真澄は車を出した。
やがて車はマヤのマンションに到着した。マンションの駐車場にとりあえず真澄は車を置いた。
「そら、マヤ、着いたぞ。歩けるか?」
「う…ん、速水さん?」
「危ないところだったんだぞ。」
「ああ…あたし…酔っちゃって…」
真澄はマヤを支えて歩き、合い鍵でマヤを部屋に連れて入った。
そのままマヤを寝室へ抱き上げて連れて行き、ベッドに寝かせた。
「今日は休むんだな。お説教はまた後日だ。おやすみ。」
言って真澄はマヤに軽くくちづけた。
そして寝室の灯りを絞ると、マヤの部屋に鍵をかけ、マヤのマンションを後にした。
マヤが他の男に手を出される、考えただけでその嫌悪感に、真澄は胸を悪くした。
ともあれ、今日は無事で良かった。
黒沢聡、二度とマヤとは共演させるものか。真澄は固く決心していた。
後日、黒沢もマヤも、個別に真澄に直々に社長室に呼び出され、こってりと説教された。
「言い寄る男のあしらいぐらい、いい加減覚えるんだな。毎回毎回冷や冷やされられるのはご免だぞ。」
「はい…ごめんなさい…」
「芸能界は鬼千匹だ。マヤ、それはよくよく知っているだろう?」
「もう、きみは昔とは違う。『紅天女』を背負って立っているんだ。くれぐれも周囲には気を配ることだ。」
「はい…」
「それに…今ではマヤ、きみの身体はきみ一人のものじゃない。俺のものでもあるんだ。もっと自分を大事にしてくれ。」
「速水さん…」
「ごめんなさい、心配かけて…」
マヤは悄然と項垂れた。
「判ればいい。また近々、スケジュールの合う時に夜、逢おう。いいな?」
「はい、速水さん…」
その次の逢瀬は、ふたりにとって、濃い一夜となった。
真澄は夜通しの抱擁でマヤの愛を確かめ、マヤは真澄の深い愛に抱きとめられ、心身共に真澄の愛を刻み込んだ。
この揺るがぬ愛の前では、どんな誘惑も、その力を失うだろう。
その確信を得られるまで、真澄はマヤを抱いて、離すことはなかった。
終わり
2002/10/28
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
