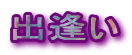
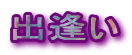
| 272727番ゲット・ひいらぎ様リクエスト:「真澄さんと、聖さんの初めて会ったときのお話」 これも、とっても読んでみたいお話しなんです。 こちらについては、つべこべ申しません、 ユーリさんの思うがままの二人の出会いを、読んでみたいんです。 ※2つリクエストをいただきましたが、2つめのこちらの方で参りたいと思います。 |
Sometimes I feel like a motherless child 時には母のない子のように
Sometimes I feel like a motherless child, 時には母のない子のように
A long ways from home; ―― 故郷を離れている気持ち
True biliever, まことの信者
A long ways from home, ―― 故郷を離れている気持ち
Sometimes I feel like I'm almos' gone, 時にはこの世を抜けだして
Way up in the heavenly land; ―― 天の御国にのぼった気持ち
True biliever, まことの信者
Way up in the heavenly land; ―― 天の御国に昇った気持ち
A long ways from home,―― 故郷を離れている気持ち
(「黒人霊歌集」 バーバラ・ヘンドリックス)
真澄が高校3年の夏休み。
或る日曜日、真澄は英介から、来客があるので自宅で待機するようにと指示を受けていた。
自宅に来客といえば、仕事関連の人脈の挨拶伺いだろうと、真澄は端的に予想し、自室で時間が来るのを待っていた。
こんどはどんな御仁か。大の大人が英介のみならず、真澄にも媚びへつらう姿には、真澄は心底辟易していた。
今日もおおかた、そんなところだろう。
真澄は読んでいた経済誌から顔を上げ、フッと溜め息を漏らした。
午後二時近く。時間か。
真澄はつと立ち上がると、応接室に向かった。
応接室にはすでに英介が控えていた。
「いいか、真澄。今日の客は極秘中の極秘人物だ。しかと心しておけ。」
「…はい、お義父さん…。」
それほどの極秘事項ならば、白昼堂々、自宅で会見していいものなのか、ふと真澄は疑問に思ったが、あえて口には出さなかった。
午後二時。ちょうどに、応接室のドアがノックされた。
「入りたまえ。」
英介が応じる。
重厚なドアを開けて入ってきた人物を一瞥して、真澄は息を飲んだ。
少年――
真澄と同じくらいか。
「おう聖、よく来た。紹介しよう。これが真澄だ。」
「真澄さま、初めまして。聖 唐人です。」
聖、と呼ばれたその少年は、真澄に向かって丁寧に頭を下げた。
「あ、ああ。よろしく。速水真澄です。」
「真澄、この聖父子は大都の“影”の部下だ。会社の重役たちでさえ、聖の存在は知らない。」
「“影”?」
真澄は聖に、まじまじと見入った。
触れてしまえばそのまま泡となって消えてしまいそうな、あまりに儚く脆いその存在感、佇まい。ごく繊細な造型の端正な横顔。
人生の表街道を歩いている真澄が初めて触れる、それは人生の深い翳りの世界だった。
英介に促されて、聖はソファに腰を下ろした。
その立ち居振る舞いも、なんとも忍びやかだった。
聖はその独特の穏やかな口調で、淡々と話し始めた。
「十年前…破産に追い込まれ一家心中しようとしていた父を速水社長が助けて下さらなければ今頃は僕もここにこうしてはいられません。」
「あの時母と妹を失い、父と僕は戸籍を無くしました。“影”として生きる以外何が出来ましょう。速水社長が父と僕に活路を与えて下さったのです。」
「父が病気で“影”としての働きが出来なくなってからもこの3年、父の入院費をはじめ僕の学費や生活の一切の面倒を見てきて下さいました。」
「そのご恩に報いるためにも、“影”としてわずかでもお役に立てるのなら、それこそ本望です。」
「来春、高校を卒業します。真澄さまの影の部下として、本格的に稼働開始します。」
「一度は死にかけたこの身、真澄さまのため、いつでも命を捨てる覚悟はできています。」
物静かな淡々とした語りの中にも、確たる意志が閃光のように閃き、密かに秘められていた。
「そういうわけだ。真澄。聖の父にはよくやってもらった。今度は真澄、お前がこの聖に尽くして貰え。」
「真澄、お前にもいずれ会社の裏社会を掌握してもらう。その時こそ、この聖がお前の貴重な片腕になるだろう。」
「はい、お義父さん…判りました。」
真澄は聖を振り返って、神妙に口にした。
「では、聖、今後ともよろしく頼む。」
「はい、なんなりと。真澄さま。これが僕の連絡先です。」
聖は電話番号を書いたメモを真澄に手渡した。
「ところで、聖、父上の具合はどうだ?」
「はい、あまりよくありません…。一進一退で…。」
「そうか。命あっての物種だ。お前もくれぐれも命は大切に、な。」
「はい…ありがとうございます…。」
日頃非情冷徹な英介が聖に示した温情に、真澄は以外な面もちでいた。それほど、この聖父子との関係は深いのだろうか。
関係…いや、絆、なのだろうか。真澄はひとり思い巡らした。
真澄はこの日初めて聖の存在を知ったが、聖の方は父親から真澄の後継者教育のことは聞き知らされていた。
聖にとっては、待ちに待った初対面、と言っていい。
父親から聞き覚えた真澄の姿は、聖の予想にたがわず、聡明そうであり、凛とした意志の強さが、その鮮やかな光を放つ双眸から窺われた。
聖はひと目見て、真澄に心惹かれた。
このかたのためになら、存分に仕えられる。
たとえ身を挺してでも。
聖は意を新たにして、改めて眩しげに真澄を見つめた。
その日は紹介だけで、ごく短時間で聖は屋敷を辞していった。
翌日、早々に真澄は聖に連絡を取った。
「ああ、聖か。早速だが一件調べて貰いたい。最近、大都に急接近してくる運輸会社がある。
判る範囲でいい。裏がとれないか。日南運輸だ。」
“日にちの日に南で日南運輸でございますね?”
電話口の向こうの聖の声は、前日と変わらず淡々と穏やかだった。
「そうだ。できるか?」
“3日後にもう一度ご連絡下さい。ご用意しておきます。”
「判った。では頼む。」
“はい。お任せ下さい。”
聖は父親の残した裏のルートを丁寧に当たり、初仕事としては上々の仕事をした。3日は、余裕の日程だった。
木曜、真澄から連絡が入る。
“首尾はどうだ?”
「はい。完了しております。受け渡しはどのように致しますか?」
“それだが、この土日、うちの伊豆の別荘に一緒に行ってくれないか。”
“きみにも是非覚えておいて欲しい場所だ。”
「それは…構いませんが。」
“では土曜の朝7時に、屋敷に来てくれ。待っている。”
「承知いたしました。」
土曜、聖が早朝速水邸に赴くと、真澄がすでに玄関前に立ち、車の用意をさせて待っていた。
「おはようございます、真澄さま。」
「早くから済まないな。さあ、乗りたまえ。」
真澄に促されて、聖は黒塗りの車の後部座席に乗り込んだ。
車が発進した。
「これがお約束の調査です。」
聖はブリーフケースから書類を取り出すと、真澄に手渡した。
伊豆へ向かう車中で、真澄はその書類に素早く目を走らせた。
書類は、完璧な出来だった。
当該会社の社歴から、この10年の実績、係累関係、資本金、経常利益の推移といった表の情報のみならず、
政官界とのコネクションから社長の女性関係まで洗いざらい述べ連ねられていた。
そして肝心の大都への接近目的は、運輸業務部門への合弁を目的としたプロジェクトチームが組まれている、との内部調査報告で
締めくくられていた。
なるほど、これが“影”の仕事か。真澄は内心舌を巻き、“影”の存在に心底得心した。
朝の高速道路、車窓の風景が珍しいのか、聖は窓の外を心地よさそうに眺め入っていた。
「ありがとう。ご苦労だった。よく調べたな。」
真澄の言葉に、聖は振り向いた。
「“影”として、当然のことですから。」
幽かに微笑んで、物静かに、聖は受け流す。
「これからも、よろしく頼む。」
「ええ、もちろんです。真澄さま。」
車は軽快に走り、真澄の伊豆の別荘に到着した。
運転士に明日午後の迎えを指示し、真澄は聖を伴って古めかしい別荘に入った。
別荘番が用意していた遅い朝食兼昼食をとり、ひと休みしたところで、真澄は聖を誘った。
「泳がないか?聖、きみ、泳ぎは?」
「ええ、泳げますよ。」
リビング奥の籐の箪笥から真澄は2着分の水着を取り出すと、片方を聖に渡した。
「よし。行こう。着替えるぞ。」
言って真澄は手早くシャツのボタンを外していく。
聖も、躊躇いながら、きっちりと着込んだシャツを脱いだ。
真澄は聖に背を向けて全裸になると、水着を付けた。
聖も、水着姿になる。
聖は、真澄のよく発達して均整のとれた、少年期の終わりの裸体の美しさに目を奪われた。
この夏すでに泳いでいるのだろう、よく日焼けして引き締まり、つややかなハリのある肌の、その裸体。聖は見惚れた。
「意外と…」
言い淀んだ真澄に、怪訝そうに聖が窺う。
「ほっそりしているのに、しっかり筋肉がついているじゃないか。」
聖は少し含羞んで、真澄に答えた。
「護身術はひととおり身につけていますから…。」
聖も、その細身の体に、ナイフのように鋭い筋肉を身に纏っていた。
真澄はバスルームからサンオイルと日焼け止めを持ってくると、日焼け止めを聖に渡した。
「ほら、日焼け止めだ。塗っておかないと、そんなに白いままじゃあ火ぶくれになるぞ。」
「…ありがとうございます。」
「背中を塗ってやろう。」
「いえ、自分でできますから…!」
「いいから!」
聖に否やを言わせず、真澄は日焼け止めを聖の背に手早く塗りつけていく。
男にしては肌理の詰んだ、しみ一つ無いなめらかな背中だった。
「綺麗な肌だな。」
聖は言葉を失って、俯いた。
一通り真澄が聖の背中にクリームを塗り終えた。
「…どうもありがとうございます。あとは自分で…」
「ああ。」
真澄は今度は自分の体にサンオイルを浴びせかけ、さっとひと塗りした。
聖は、脱いだ衣服を慎ましくきちんとたたんでソファの端に置いた。
「よし、行こう。」
玄関に出してあったビーチサンダルを履いて、ふたりは浜辺に降りた。
真夏の午後の太陽はギラギラと眩しく輝き、ふたりの肌を焼いた。
海は穏やかに凪いで、ふたりを迎えていた。
軽く手足を振ると、サンダルを砂浜に脱ぎ捨て、真澄は海に入っていった。聖もそれに従う。
「競争するか。疲れたら言ってくれ。やめにするから。」
「はい。真澄さま。」
「行くぞ。」
言うが早いか、真澄は沖に向かって、素早いスピードで泳ぎ始めた。
聖はピタリと真澄についていった。
全力で100メートルは泳いだだろうか、真澄は呼吸を弾ませて、いったん泳ぎを止めた。
「なかなかやるじゃないか。華奢な見かけによらないな。」
ゆっくりと海水をかき分けながら、真澄は聖に声をかけた。
「真澄さまにお仕えする時のために、鍛えてありますから。」
聖も荒い息の下から真澄に答えた。
「それは、ありがたいことだ。」
真澄はくるりと体を裏返すと、背泳ぎで海に体を投げ出し、ゆっくりと遊泳した。
聖は真澄から離れず、真澄の傍らについて泳いでいった。
午後一杯、海辺で過ごすと、ふたりは別荘に戻った。
それぞれシャワーを使って着替え、西陽の傾くテラスで、冷たい飲み物をとり、喉を潤す。
水平線の彼方に傾く夏の太陽は、真澄の横顔に深い影を落とした。
語ることなく、話すことなく、その声も聞こえないのに、聖には真澄の言葉にならない心の叫びが聞こえたような気がした。
その寂寥は、聖の胸を打った。
まだ若く、寄る辺ない魂は、真澄の身体から出て空高く浮遊し、西空に拡散していくようだった。
聖は黙って、真澄を見つめていた。
「…この別荘は――」
真澄が徐に口を開いた。
「俺の隠れ家のようなものだ。ここに来ると、自由になれる。」
何からの自由なのか。言わずとも聖には判ったように思う。
速水家の跡取りとしての仮面を外した、本来の真澄自身に立ち返る時間が、この別荘には流れているのだろう。
言わずとも通ずる。
聖が真澄の言わんとするところのものを確実に受け取っているのを、真澄もまた感じていた。
同年代の友人など作らずにきた真澄にとって、聖との鋭敏な意志の疎通は、真澄にはひどく新鮮だった。
聖、この少年になら、通常他人に対するようには心の壁を作る必要はないのかもしれない。
その真澄の思考をなぞるように、聖が言葉にした。
「僕は、真澄さまの影です。これからも。いつまでも。」
「聖…」
ふたりは夕食を済ませ、テレビのニュースにひとしきり見入り、新聞を読んだ。
ゆったりした時間が、静かに流れていった。
聖は物静かに、真澄の傍らに侍った。
「11時か。そろそろ寝るか。きみは客室を使ってくれ。」
「はい。真澄さま。」
ふたりは2階の寝室へ上がった。
「では、おやすみなさいませ。」
「ああ。おやすみ。」
朝が早かったこともあり、午後に遠泳した疲れで、聖はすぐに寝入っていた。
が、異様なきな臭い息苦しさで、喉が詰まり、目を覚ました。
時刻は午前2時過ぎ。部屋には煙が充満し、パチパチと炎で樹のはぜる音が聞こえてきた。
――火事!
聖は飛び起きると、真澄の寝室に飛び込んだ。
「真澄さま!真澄さま!」
聖は熟睡している真澄を揺り起こした。
「火事です!真澄さま!」
「…なん、だって…?」
「早くお逃げ下さい!」
真澄はハタと覚醒し、布団から跳ね起きた。
枕元の電話で手早く消防を呼ぶと、真澄は叫んだ。
「外へ出るぞ!」
寝間着のままふたりは階段を駆け下り、玄関の扉を開けた。
途端にゴウと、炎が襲いかかった。
「火元だ!」
真澄は素早く扉を閉めると、
「こっちだ、聖!」
聖の手をとると勝手口に走った。スリッパのまま、ふたりは勝手口からようよう別荘を抜けだした。
「浜へ降りるぞ!」
「はい!」
古い建物は火の回りが早く、ふたりが抜け出した直後には、火は建物全体に回っていた。
暗がりの中、燃えさかる別荘の火影を頼りに、ふたりは浜辺へ降りる急な石段を降りた。
半分ほど降りると、スリッパで真澄は足を滑らせ、
「うわっ!」
危うくバランスを崩した。
「危ない!」
聖は真澄を石段に向かって突き飛ばすと、今度は聖がバランスを崩し、石段を転がり落ちていった。
「聖!」
真澄は今度は慎重に石段を駆け下り、蹲った聖のもとに駆け寄った。
「大丈夫か!?」
「う…」
最初の衝撃が去ると、聖はゆっくり身を起こした。
「怪我は!?」
「ああ…大丈夫です…肩を少し…打っただけです…」
真澄は聖を抱き起こした。
「つっ……」
「済まない…俺のために…」
「真澄さまさえご無事なら…お守りするのが僕の役目ですから…」
ふたりは浜辺に腰を下ろし、焼け落ちる別荘を黙って見入っていた。
やがて消防車が到着し、ほぼ全焼した建物を念入りに消火した。
「おーい!誰か居ないかー!」
消防団員が見回りに来た。
「こっちだ!」
真澄が団員を呼んだ。
「あんたら、火元の家の人達かね?怪我はないか?」
「大丈夫です。東京の自宅に連絡を入れて頂けますか。迎えを待ちますから。電話番号は…」
消防団員はトランシーバーで真澄の告げた電話番号を消防本部に連絡した。
「じき夜も明ける。あんたら、火元には近づくんじゃないぞ。」
「はい。どうもお世話さまでした。」
これで、あとは東京から迎えが来るのを待つだけだ。
真澄と聖は、浜辺に腰を下ろして、夜明けを待った。
海の水平線彼方には、下弦の半月が沈もうとしていた。
「真澄さま、せっかくの隠れ家が焼けてしまいましたね…。」
「なに、またすぐ義父が新築するさ。それにしても、また火事か…。」
「以前お屋敷も火事に遭われたと聞いています。」
「…ああ。あの火事で、母を亡くした。」
「あれから、もう4年か…。」
しばし、沈黙すると、聖は静かに口ずさんだ。
「Sometimes I feel like a motherless child,…」
「時には母のない子のように?」
「私も母を亡くしています。真澄さま。」
聖は続けて、その歌を淡々と歌った。
黒人霊歌独特の陰影に満ち、憂愁に満ちた美しいバラードだった。
聖の繊細な感受性が、歌唱のそこここに溢れ出て、真澄の尖った神経を鎮め、慰めた。
初対面から1週間、この夜のひと時こそ、真澄は真の意味で、聖という人間に出逢った思いだった。
聖を前にしても笑顔を見せていなかった真澄だが、闇の中、聖のもの柔らかな歌声を聞きながら、ふっと真澄は微笑みをもらしていた。
この聖ならば、心許せる唯一の部下にもなってくれよう。
真澄は開かれた未来に、遥かに思いを馳せた。
聖の歌声は、岸辺に寄せる波風にのって、虚空高く吸いこまれていった。
夏の夜明けは早い。午前4時。空は白々と明るくなり、水平線が燃えるように赤く染まった。
じきに東京からの迎えが来るだろう。
「夜明けですね。」
「ああ。命拾いした。助かったよ。ありがとう。」
「真澄さま、御身お大切に。」
「きみこそ、だぞ。これからもよろしくな。」
「はい。真澄さま。」
――『僕はあなたの影です。これからも。いつまでも。』――
この少年の日の出逢いから、その後長きに渡って、聖は真澄の文字通り腹心となり、
真澄のただ一つの恋の、唯一の理解者となってゆく。
その未来を、この日のふたりは、いまだ知らない。
終わり
2002/9/26
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
